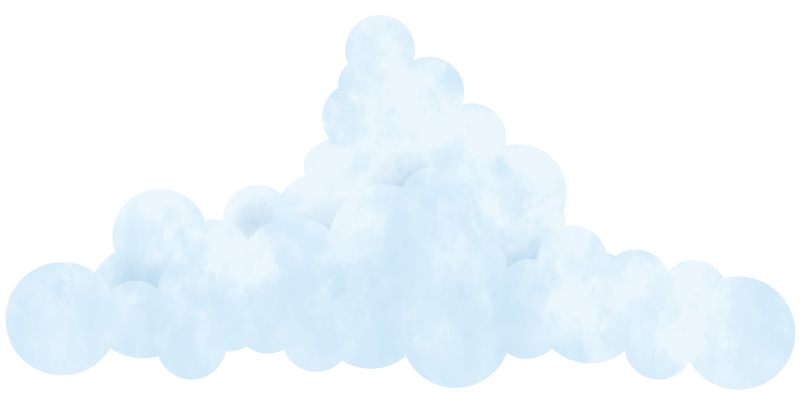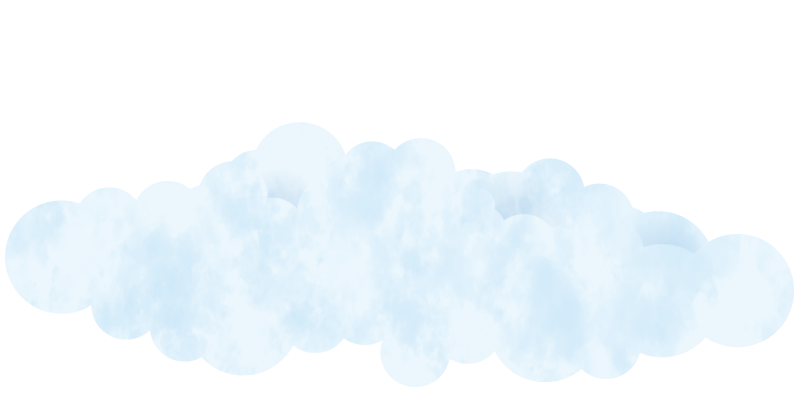光円がつくった道
今から、およそ150年前のことです。大三島肥海の金剛寺に第十世住職光円という和尚さんがやって来ました。
光円は、年は31才で、りっぱな学問をおさめている上に、とても心のやさしい人でした。当時の村は松山のとの様がおさめていましたが、村の家はわずかでした。光円和尚は、昼も夜もこの村がゆたかな村になることを考え続けました。
そこで考えついたのが、道路をつくり、橋をかけることでした。その当時の道は、人一人通るのがやっとで、今のような広い道路はありませんでした。
荷物は、米、麦、大豆、たきぎなどでしたが、かたにかついだり、馬の背にのせたりして運んでいたので、たいへんなことでした。
まず、目をつけたのは、肥海と大見を明日、宮浦につなぐ海岸の道路でした。そのころの海岸には道はなく、村人たちは苦しい山道をこえて行き来していました。海岸も通れないことはないのですが、岩づたいに行かなけれなならないので、たいへんきけんなことでした。中には、海に落ちれなくなった人までいました。
 金剛寺
金剛寺 大三島町肥海
大三島町肥海
光円は、道明まで毎日出かけていろいろと調べました。そして、とうとう工事に取りかかりました。かたい岩なので、仕事はなかなかはかどりませんでした。光円は、休むことなくみんなの先頭に立って働き続けました。
そして、半年間、努力のかいあってとてもりっぱな道路ができあがリました。1863年8月のことでした。石がきがついたはば2m、長さ1500mの道路です。この道のおかげで、村の人たちのくらしも、だんだんゆたかになってきました。
光円は、70オでなくなりましたが、今でも人々にしたわれています。
 光円がつくった道の今の様子
光円がつくった道の今の様子 光円和尚
光円和尚