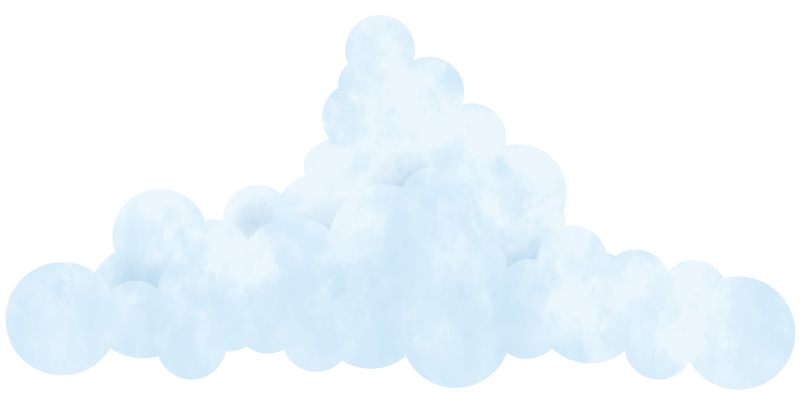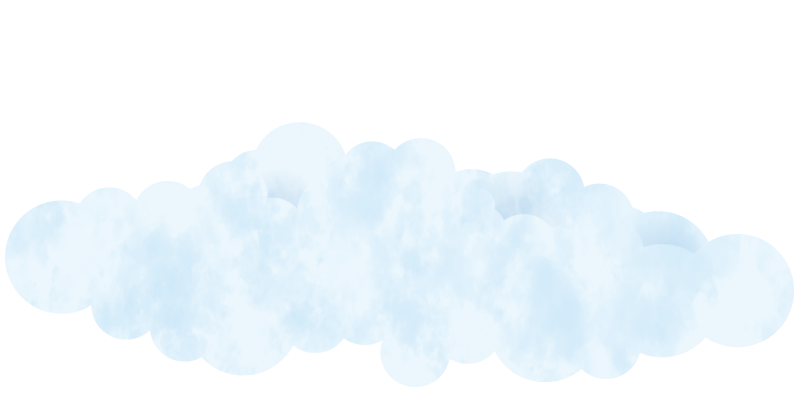4. 文化や産業の発てんにつくした人
今治市の文化や産業の発てんにつくした人たちについて調べてみましょう。
今治市は、日本一のタオル生産地であるとともに、造船・海運が栄える世界有数の海事都市でもあります。
また 今治 城や大山衹神社をはじめとして、多くの神社や寺院などに伝えられるものから、古くより文化の里としても発てんしてきたことがわかります。
この発てんのうらには、多くの人の努力や働きがあったことがうかがえます。
文化と医学につくす 半井梧庵
 半井梧庵
半井梧庵 梧庵が書いた書
梧庵が書いた書
今はなくなりましたが、昔、※天然痘というおそろしい伝せん病が流行していました。この病気をふせぐには、種痘という方法で予ぼうするのですが、この方法を今治の人たちにほどこした一人が、半井梧庵です。
今から200年ほど前に生まれた梧庵の家は、代々医者を仕事としていました。しかし、梧庵がまだ子どものときに父がなくなってしまったため、つらい生活をしました。何年か後に京都へ行き、医学の勉強をしましたが、日本や中国、西洋のさまざまな学問もおさめました。特に、※和歌について研究を深め、40才のときには、『歌格類選』という本を完成させました。
また、『伊予国風土記』という本がなくなってしまったことを知り、残念に思った梧庵は、愛媛県のきょう土の様子をあらわした本をつくろと考えました。そこで、梧庵は、神社やお寺、古いいせきをたずねたり、古い書物を調べたりして、『愛媛面影』(五巻)という本を完成させました。
その後、今治藩の※藩校「克明館」の先生として、多くの人々を指どうしました。
梧庵は、医者として多くの人の命を救いました。また学者としてたくさんの本をあらわしました。そのほかにもたくさんの※功せきを残し、今治の文化の発てんのためにつくしました。
※天然痘
伝せん病の一つで、体中にはれものができ、死んでしまうことも多かった病気
※和歌
古くから日本に伝わる詩。今では、短歌とよばれています。
※風土記
今から1200年くらい前につくられた本で、地方ごとに、土地の様子や人々の暮らしが書いてありました。
※藩校
江戸時代、藩がつくった武士が学ぶための学校。
※功せき
りっぱな働き。