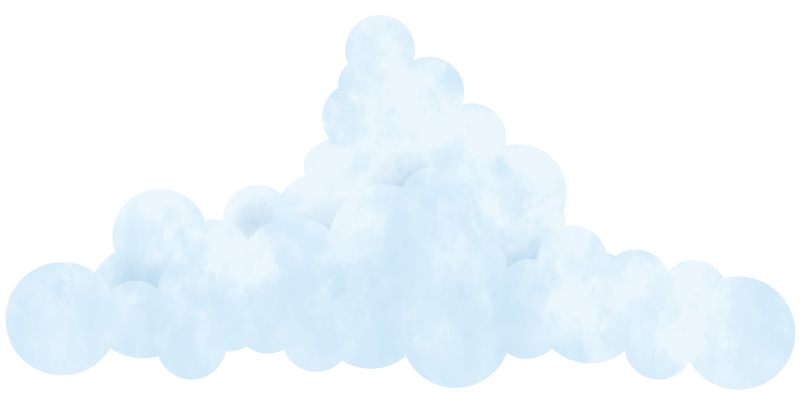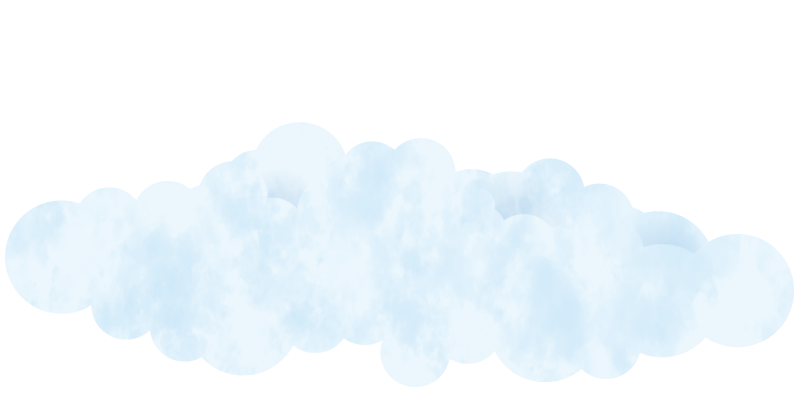産業の発てんにつくす 阿部平助
 阿部平助
阿部平助 阿部平助 胸像
阿部平助 胸像
今治市は、今や日本一のタオルの産地に成長しました。今から120年ほど前に、この今治の地で初めてタオルの生産を始めた人が阿部平助です。
平助と綿織物との最初の出会いは、※綿替木綿商としてでした。1890年、平助は※綿ネルを織り始めました。そのころ、今治の※綿業がだんだんおとろえていく様子を見た平助は、白木綿に代わる新しい織物はないものかと織物の産地をたずねて歩きました。たまたま大阪へ出ちょうしたときに、大阪市内の小売店で初めてタオルにめぐり会いました。平助は、初めてタオルを手にし、今までの綿織物のはだざわりとはまったくちがう感しょくにおどろきました。そして、平助はタオルを買って帰り、弟の利三郎と力を合わせ、タオルの織り方の研究に取り組みました。研究を重ねた結果、泉州(今の大阪)から「打ち出し織機」という手織機を4台買って改ぞうし、タオルを織りました。1894年12月のことでした。これが今治で織られた最初のタオルでした。
次の年には、織機を10台にふやしましたが、不幸にも工場は火事にあい、全部焼けてしまいました。平助はそのような苦労にも負けず、今度は織機を30台そなえた新しい工場をつくり、ふたたびタオルのせいぞうを始めました。しかし、織機は手動式で、改ぞうしたものであったため、ずい分苦労しました。せいのうも悪く、平助にとって満足のいくものではありませんでした。それでも平助は、出ちょうのたびに熱心にいろいろな人の意見を聞いて、それを取り入れながらタオルの生産を続けました。1916年には,綿ネルの生産に力を入れることになったため、残念ながらタオルの生産をやめることになりました。しかし、その後も平助の努力を多くの人が受けつぎ,今治はタオルのまちとして、発てんしました。
※綿替木綿商
実のついた綿を農家にわたし、その綿からつくった白木綿の半分を受け取り、それを売る仕事
※綿ネル
冬物の衣服などに使われ、表面がふわふわしていて、あたたかい布
※綿業
綿からつくった糸で布を織ったり、品物をつくったりする仕事をまとめた言い方。